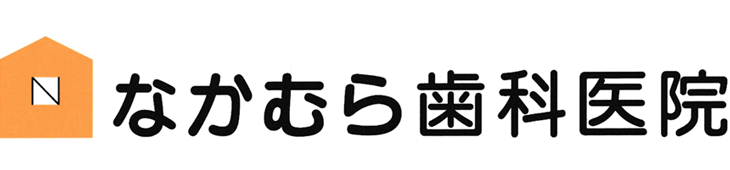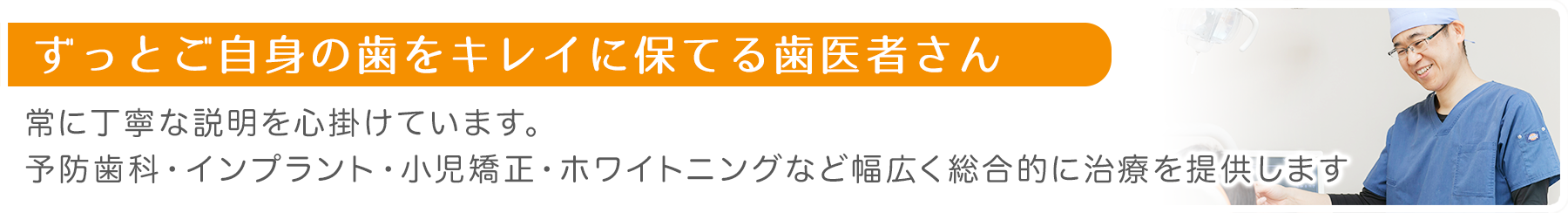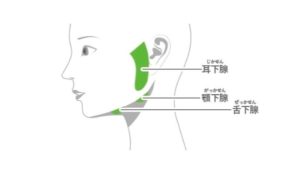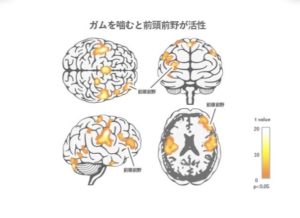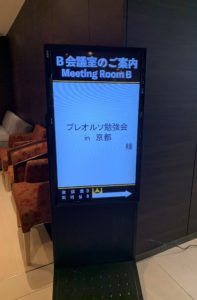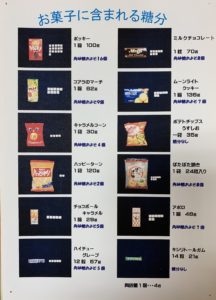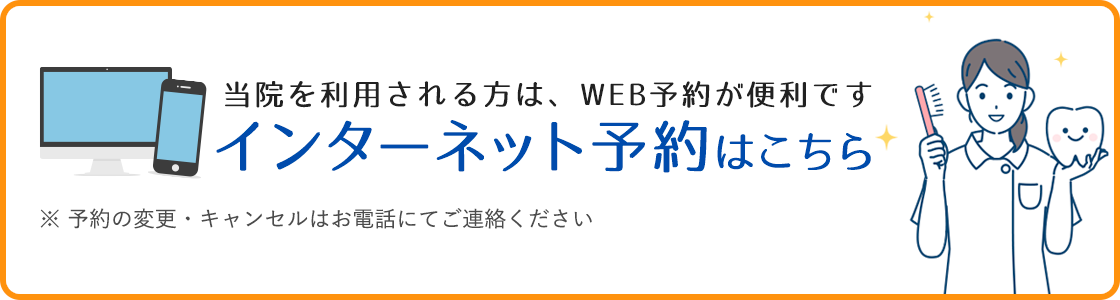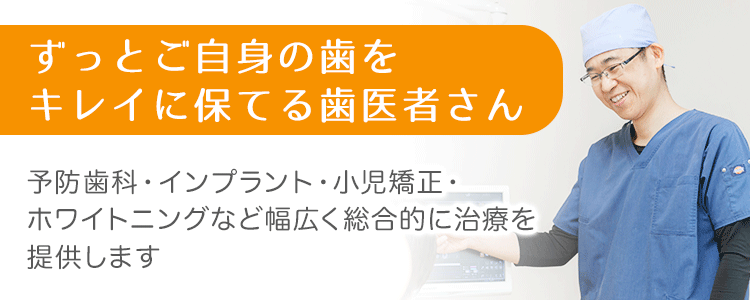人工歯根として扱われているチタン
チタン材料の開発当初はロケットや航空機に使用されていましたが、製造技術の向上とともに医療にも応用されるようになりました。人工歯根の他にはの他に人工骨・心臓弁・心臓ペースメーカーなどに使用されています。
チタンが広く応用される理由はその材料特性にあります。チタンは強度が高く、軽く、錆びにくいことが特徴です。
強度の点ではアルミニウムの約3倍、鉄の約2倍です。軽さの点では銅の約50%、鉄の約60%の軽さです。
錆びにくさでは白金に匹敵します。
なによりも他の金属に比べて金属アレルギーを起こしにくいのです。また骨との結合性もあるので顎の骨に埋入するインプラントとして最適なのです。
インプラントでも腐食することがあります。
チタンには表面に非常に強固な酸化膜が覆われています。その酸化膜が破れたり、壊れたらいくらチタンでも腐食がはじまります。ただすぐに強固な酸化膜が再生するため腐食が連続的に進行せずに止まることが多いのです。
この酸化膜を溶解するのが実は、フッ素なのです。
ですからフッ化物歯面塗布剤を使用する場合はチタンに接触しないよう注意を払う必要があります。
ホームケアで使用される低濃度フッ素配合の歯磨剤においてもインプラントは腐食リスクがあります。
市販の歯磨剤の多くは950~1450ppmのフッ素が含有されています。
実際の口腔内ではフッ素が投入される時間は短くブラッシング中に唾液で希釈されフッ素濃度が下がります。歯磨剤そのものにもPh緩衝剤が含まれていて、また唾液にでも緩衝されますから口腔内が酸性にならないよううまく調整されています。
逆に言えばチタンが腐食するようなフッ素濃度と酸性度が持続することはほとんど無いと考えられます。
とはいえ、チタンにとっての腐食条件が揃うと一時的な腐食が発生します。具体的には食後や酸性の飲食物を摂取した後にすぐに高濃度のフッ素配合歯磨剤ですぐに歯磨きすれば瞬間的に腐食条件が揃うことになるかもしれません。それが長期間累積することによって穴があく腐食や表面がザラザラする粗造化を招く可能性があります。
腐食が累積するとどうなるか
腐食による細かな穴が少しずつでも大きくなるとインプラントに咬合力などの力がかかった時に、その部分に力が集中して穴が無い場合よりも破折しやすくなります。また表面の多数の穴やザラザラ化は清掃性が損なわれますので、インプラント周囲炎の発生のリスクが高まります。インプラント周囲炎はインプラント周辺に起こる炎症で、インプラントを支える骨が減っていく病気です。
チタンインプラントをされている方は激増しています。
インプラントを長期間安心安全に使用するためにはホームケアと定期的なメンテナンスは必須です。
ホームケアにはフッ素配合歯磨剤を用いてブラッシングすることが多いと考えられます。
インプラントの腐食発生リスクを下げるためには、口腔内を酸性にしないこととインプラント周囲にプラークを残さないことが何よりも重要です。
フッ素の天然歯への有効性は言うまでもありません。口腔内の条件が整っている限りはフッ素を活用すべきです。しかしながら口腔内が酸性、もしくはインプラント周囲のプラークコントロールが不良である時には、フッ素を配合しない歯磨剤を使用するかフッ素配合歯磨剤を使用する場合はインプラントのところ以外の場所からブラッシングを始めるとよいでしょう。