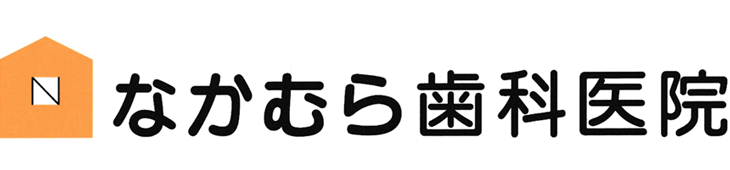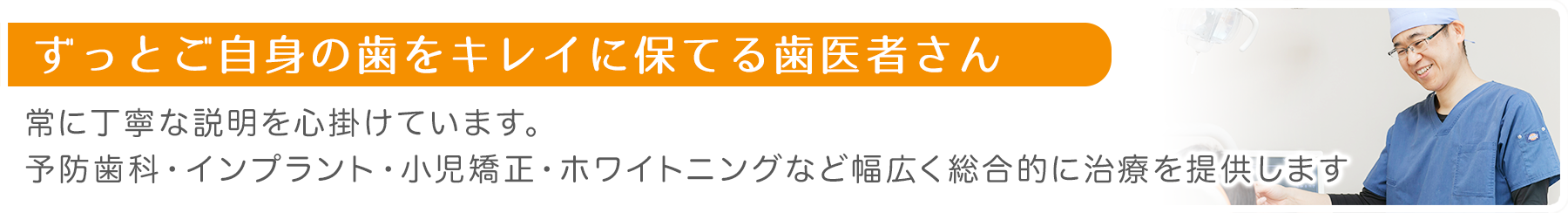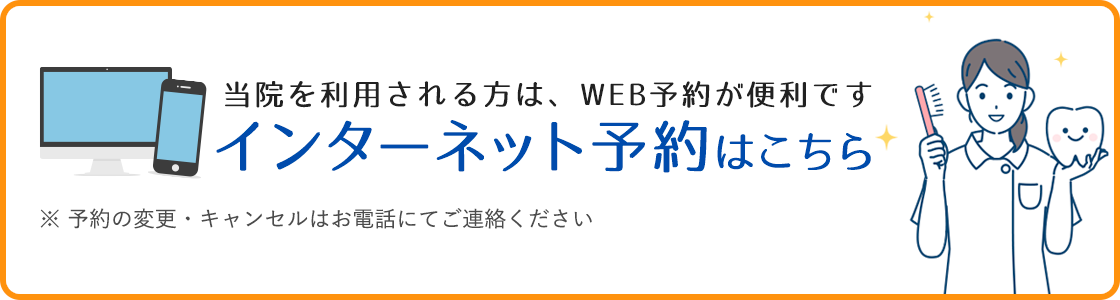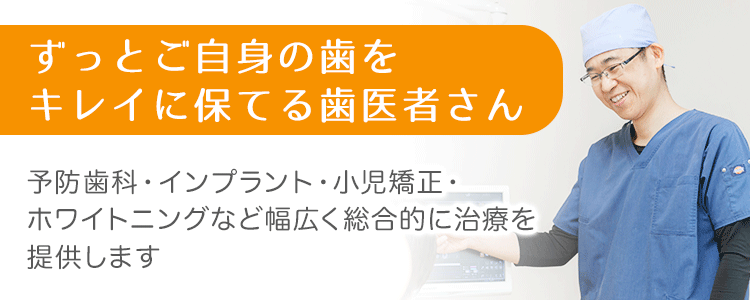目次
腸内細菌叢を育む食生活 そして口腔内細菌とのかかわり
前回お話した通り、日本人に合った腸内細菌叢―腸管―脳軸(Gut-Microbiota-Brain Axis)を整えることはとても重要です。そのための、乳幼児期・学童期・成人期に応じた具体的な食事例と、1週間のモデル献立をご紹介します。すべて一般家庭で再現可能な和食中心のスタイルで、乳酸菌・食物繊維・発酵食品・オメガ3脂肪酸などの「腸―脳をつなぐ栄養素」を意識しています。
乳幼児期(離乳食後期〜2歳頃)

ポイントは、発酵食品(少量の味噌、納豆、ぬか漬け)、食物繊維(野菜、芋、果物、豆類)など薄味・少量を複数回摂取できるとよいでしょう。手は汚れますが、手づかみ食べを取り入れ、自律性と満足感を高めるようにしてみてください。この時期は二度と戻ってきません。砂糖控えめにするのもポイントです。
1歳半頃〜
一例です。
朝食 おかゆ+小松菜としらすの和え物+バナナ
昼食 軟飯+鶏そぼろ+かぼちゃ煮+味噌汁(豆腐・わかめ)
おやつ 焼き芋、バナナ、プレーンヨーグルト
夕食 ごはん+納豆+さつまいも+野菜の味噌汁+すりおろしりんご
学童期 小学生
ポイントは腸と脳を支える朝ごはんの質がカギです。腸内多様性を意識して、日替わりで色んな野菜や穀物を使うようにしてみてくさい。発酵食品(味噌、ヨーグルト、ぬか漬け)、海藻、魚、きのこを積極的に取り入れてみましょう。雑穀・野菜・魚中心の家庭食、味噌・納豆の習慣化にしましょう。思春期(13歳~18歳)は腸内細菌が乱れやすく、ニキビ・便秘・精神不安などが起こりやすい年代です。発酵食品とプレバイオティクス(海藻、きのこなど)を摂取すると共にストレス管理に気を配ってあげてください。
一例です。
朝食 ごはん+焼き鮭+納豆+キャベツ味噌汁+りんご
昼食(弁当) 雑穀ごはん+鶏の照り焼き+ブロッコリー+卵焼き+にんじんのラぺ
夕食 玄米ごはん+さばの味噌煮+大根と油揚げの煮物+ぬか漬け+みそ汁(わかめ・しめじ)

成人期
食生活のポイントは発酵・繊維・抗炎症を意識した腸脳ケア型食事です。ストレス対策としてトリプトファン・マグネシウム・オメガ3脂肪酸を含む食材を摂るのがカギです。主食は白米ではなく雑穀や玄米、間食には甘いものより果物・ナッツを摂るようにしてみましょう。安定期だが生活習慣の影響を強く受けます。腸内炎症、便秘、ストレス性腸症候群なども起こり得るので、酵素活性を保つ食生活(玄米・豆・野菜・発酵食品)と運動を心がけましょう。
一例
朝食 オートミール+無糖ヨーグルト+キウイ+ナッツ
昼食 玄米+納豆+野菜たっぷり豚汁+きんぴらごぼう
夕食 雑穀ごはん+焼きサバ+ひじき煮+豆腐とわかめの味噌汁+ぬか漬け
1週間のレシピ集(学童〜成人共通ベース)
一例だけではなかなか続かないと思いますので、ちょっと長くなりますが一週間分を記載してみます。あくまでも例ですので、アレンジしてみてください。朝昼晩の順に記載してます。
月曜日
【朝】
玄米ごはん、わかめと豆腐の味噌汁、納豆、りんごの薄切り
ポイントは、発酵食品と食物繊維で朝の腸活をサポート。
【昼】
野菜カレー(玉ねぎ・にんじん・大豆・トマト)、雑穀ごはん、ヨーグルト
ポイントは、スパイスと食物繊維で腸内細菌を活性化。
【夜】
鯖の味噌煮、大根とにんじんの煮物、玄米、ぬか漬け、味噌汁
ポイントは、EPA・DHAと発酵食品をバランスよく。
火曜日
【朝】
オートミール、無糖ヨーグルト、バナナ、小松菜スムージー
ポイントは、食物繊維と乳酸菌で便通改善。
【昼】
いなり寿司、小松菜とごまのおひたし、野菜のぬか漬け
ポイントは、発酵+緑黄色野菜の組み合わせ。
【夜】
鶏団子と野菜のスープ(白菜・しいたけ・にんじん)、玄米ごはん、ひじきの煮物
ポイントは、たんぱく質とミネラル補給。
水曜日
【朝】
雑穀パン、ゆで卵、トマト、バナナ
ポイントは、たんぱく質とビタミンで脳と腸を活性化。
【昼】
雑穀弁当(焼き鮭、きんぴらごぼう、菜の花のおひたし)
ポイントは、魚と食物繊維をバランスよく。
【夜】
麻婆豆腐(豆腐多め)、ごはん、ブロッコリーのナムル、味噌汁
ポイントは、豆腐と発酵食品でたんぱく質と腸内環境を強化。
木曜日
【朝】
ごはん、味噌汁、納豆、キウイフルーツ
ポイントは、腸内発酵と果物の食物繊維で整腸。
【昼】
豚汁(根菜たっぷり)、おにぎり、ぬか漬け
ポイントは、発酵と食物繊維で腸内細菌に多様性を。
【夜】
さばの塩焼き、蒸しかぼちゃ、玄米、味噌汁
ポイントは、オメガ3脂肪酸とビタミンAで脳を保護。
金曜日
【朝】
甘酒(無加糖)、バナナ、ヨーグルト
ポイントは、天然の発酵甘味と乳酸菌で快腸スタート。
【昼】
和風パスタ(しめじ・小松菜・ツナ)、豆と野菜のスープ
ポイントは、植物性たんぱくと抗酸化成分を一緒に。
【夜】
冷しゃぶ(豚肉・きゅうり・トマト)、豆腐サラダ、玄米、味噌汁
ポイントは、クールダウンと腸整効果の高い組み合わせ。
土曜日
【朝】
ごはん、卵焼き、ぬか漬け、味噌汁
ポイントは土曜の朝は消化に優しい腸活和食で。
【昼】
玄米おにぎり(昆布・ごま)、具沢山味噌汁、りんご
ポイントはシンプルながら栄養バランス◎
【夜】
鮭のホイル焼き(きのこ・野菜入り)、根菜の煮物、味噌汁
ポイントは、DHA・EPAと食物繊維が腸脳をサポート。
日曜日
【朝】
発芽玄米、納豆、焼き海苔、味噌汁
ポイントは、一週間の仕上げに腸に優しい朝ごはん。
【昼】
外食(和定食・寿司・そばなど)
ポイントは、外食時も発酵・魚・野菜を意識。
【夜】
野菜たっぷり鍋(豆腐・白菜・しめじ・人参)、雑炊仕上げ
ポイントは腸にも脳にも温かく優しいごはん。
腸―脳軸を意識した食材リスト
多様性を高めるコツは「1日30品目よりも、1週間に30種以上の植物性食品」を目指すこと。多様性が脳や全身の健康を守るカギです。腸内細菌叢(マイクロバイオータ)は乳幼児期後期(およそ3歳頃)までにほぼ確立され、その後の健康・脳発達・免疫・情緒・アレルギー傾向にまで深く関与します。
発酵食品
納豆、味噌、醤油、ぬか漬け、ヨーグルト、甘酒(無加糖)

食物繊維
ごぼう、れんこん、海藻、きのこ、玄米、豆類
オメガ3脂肪酸
鯖、いわし、鮭、えごま油、亜麻仁油
抗酸化ビタミン
緑黄色野菜(にんじん、ブロッコリー)、果物(キウイ、りんご)

口から唾液が飲み込まれ、口腔内細菌が腸内細菌に影響します。
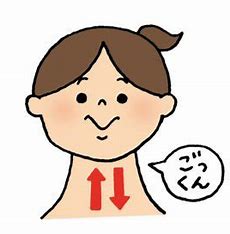
成人が1日に分泌する唾液の量は 約1〜1.5リットル(コップ5〜7杯分)とされます。この唾液は無意識に 1日あたり500〜700回程度嚥下されており、そのたびに 口腔内細菌も一緒に飲み込まれています。飲み込まれた唾液には 数百万〜数十億の細菌が含まれています。特に歯周病がある場合はさらに多くなります。通常は胃酸や胆汁により口腔内細菌の大半が死滅しますが、一部は生きたまま小腸・大腸に到達します。特にピロリ菌やフソバクテリウム属(Fusobacterium)などは胃〜腸まで生き残ることが知られています。
正常な人でも口腔菌が腸内に存在します

健康な人でも腸内には 口腔由来の細菌(ストレプトコッカス属、アクチノマイセス属など) が少量存在し、特に歯周病や口腔環境が悪い場合には、この移行が顕著になると報告されています。口腔常在菌が大腸内に異常定着すると、以下の疾患との関連が指摘されています。
Fusobacterium nucleatum
大腸粘膜への定着し炎症促進するので、大腸がんやIBD(炎症性腸疾患)の原因になる可能性があります。
Porphyromonas gingivalis(歯周病菌)
腸粘膜バリアの破壊、免疫異常 動脈硬化、糖尿病、認知症を引き起こす可能性があります。
Streptococcus属(虫歯菌など)
小腸での異常増殖すると、SIBO(小腸内細菌異常増殖症)や下痢・便秘の原因になります。
口腔ケアは腸活です!
腸内細菌に影響を及ぼさないように歯周病のケアをしておくことはとても大事です。飲み込む細菌数を減らすため、毎日の歯磨き・フロス・舌清掃が大切です。また定期的な歯科メンテナンスで歯周病菌の腸内流入を防ぎましょう。ゆっくりよく噛む・唾液を増やし、唾液の抗菌作用を活かすようにしましょう。