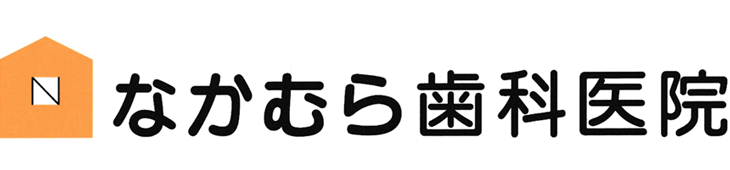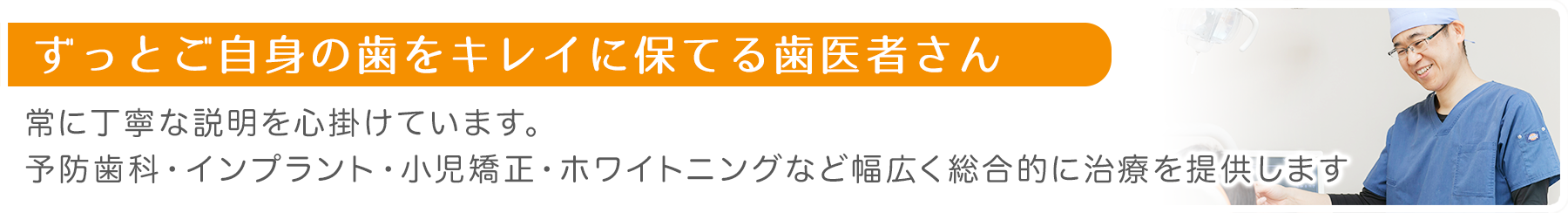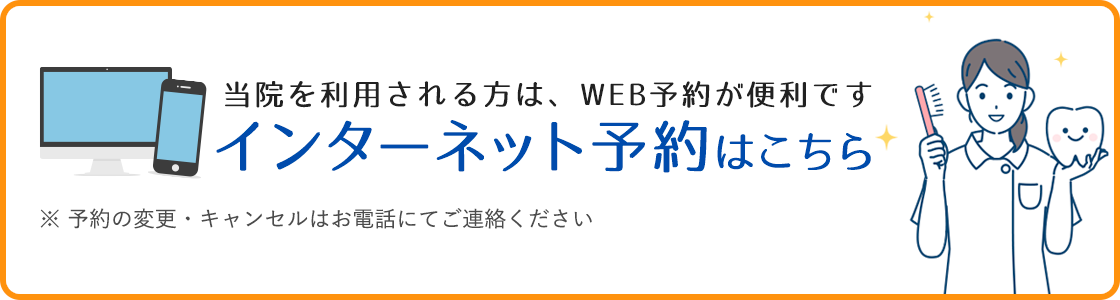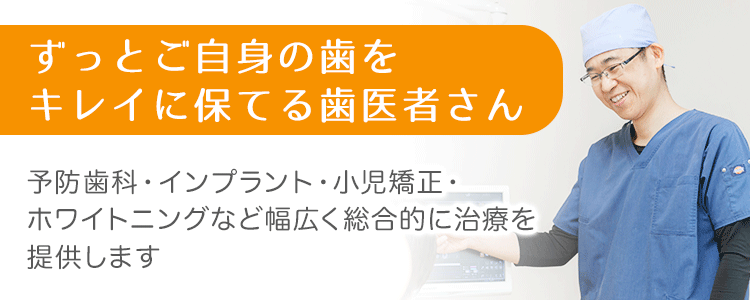日本人の多くが糖尿病や歯周炎にかかっていて、糖尿病の患者の多くが重度の歯周炎にかかっています。糖尿病の発症年齢は壮中年期以降であることが多く、患者数は増加し続けています。小児の糖尿病も急増していて、発症の若年化も進みつつあります。生活環境、食習慣、社会環境が大きく変わっていることも影響していると思います。
目次
インスリンってよく聞きますよね。それって何でしょうか
脳で考える、筋肉を動かす、脂肪を蓄える、など、体の組織を動かすには燃料が必要です。その燃料がブドウ糖です。体の組織の最小単位が細胞です。細胞の中にブドウ糖を取り込ませるために必要なのがインスリンという物質です。インスリンは膵臓から産生されます。ブドウ糖は血液を介して運ばれます。ブドウ糖が細胞に取り込まれないと血液の中のブドウ糖が多くなってしまいます。これが血糖値が上がる、という状態です。
血糖値が上がることが問題なのではない、なぜ上がっているのかが問題なのです。
血糖値が上がることでよくないことが起こります。どうして血糖値が上がるかと言えば細胞にブドウ糖を取り込む働きが出来ていないからです。インスリンの量が足りないか、インスリンそのものの機能が落ちているか、インスリンを機能させない薬を服用しているか、などが原因と考えられます。
インスリンの量がそもそも足りない、場合
簡単に言うとこれが1型糖尿病です。インスリンを産生する膵β細胞が自己免疫により破壊されてしまって、インスリン分泌が最終的に枯渇してしまう自己免疫性疾患です。インスリン分泌機能の低下や枯渇により細胞内にブドウ糖が取り込めなくなります。取り込めないと活動していけませんから、外からインスリンを自己注射していく必要があります。発症年齢は小児~思春期に多いですが、中高年でも認められます。1型糖尿病は肥満とは関係がありません。
インスリンを多く使わないと細胞に取り込めない、場合
インスリンが十分量あっても、脂肪量の増加、筋肉量の減少、運動不足などの体の変化によって同じ量のブドウ糖を細胞に取り込むのに必要なインスリン量が増えてしまう状態がおこります。(インスリン抵抗性と言います。)膵β細胞がどれだけ頑張って産生量を増やしてもなかなかブドウ糖が細胞に取り込まれず、血糖値が上がったままになります。インスリンが効きにくくなる薬を服用されている場合も同じことになっています。

2型糖尿病
2型糖尿病はインスリンの抵抗性が上がっている病態と理解されています。日本人はインスリン分泌機能低下の要素も重なっていることが多いです。患者さんごとに病態が異なります。つまりインスリンの働きが良くないという遺伝的要素に加えて、食事の習慣、運動の習慣、社会的ストレスなどの環境的な要素が加わって2型糖尿病が発症します。ですから食事療法、運動療法が必要となるのです。必要があれば薬物療法が必要になります。
HbA1cって何なん?
ブドウ糖は血液の中を直接行き来きできません。赤血球は酸素を運ぶことは学校で習ったと思います。赤血球は血色素(これがヘモグロビン)と鉄とタンパク質が結合したものです。それに糖がひっついて運ばれるとイメージしてください。ヘモグロビン全体の何%が糖と結合しているかを測定した値がHbA1cと言います。(ヘモグロビンの略称がHbです。)血糖値が高いほど血糖と結合しているヘモグロビンの割合が増えるのでHbA1cは血糖値を反映している、ということになるのです。
血糖が高いままだと何が問題になるのか
糖尿病による高血糖状態が長く続くと網膜症、腎症、神経障害、脳梗塞、狭心症・心筋梗塞、足潰瘍・足壊疽、歯周病など様々な合併症が出現します。最初の3つが3大合併症と呼ばれるものになります。
糖尿病網膜症
高血糖が続くと、眼の網膜にある毛細血管が傷つき、血管が破れると出血します。進行すれば失明します。日本の失明の原因の2位が糖尿病なのです。かなり進行しないと自覚症状がでないのがやっかいなところです。
糖尿病性腎症
高血糖が続くと、腎臓の糸球体内の毛細血管が傷ついて老廃物など不要なものをろ過することができなくなります。高血圧や塩分の過剰摂取、肥満などがあれば悪化しやすいです。腎臓の働きが低下し、尿蛋白も進行につれ増加します。尿が出にくくなってくると老廃物が体にたまり、むくみや息切れ、食欲不振などの症状も現れてきます。最終的に腎不全となって人工透析になってしまうことがあります。新規に人工透析を始める方の約半数が糖尿病性腎症です。
糖尿病性神経障害
高血糖が続くと神経の働きも障害されるようになります。末梢神経障害の足の痺れ、痛み、冷え、足のつり、自律神経障害の立ち眩み、排尿障害、便秘、下痢、足感覚の低下、などの症状が出ます。
動脈硬化性疾患
3大合併症ではありませんが、高血糖が続くと動脈硬化が進みます。心筋梗塞、脳梗塞、足の壊疽(足先に栄養が行かなくて腐敗することです。最悪の場合切断します。)高血圧や脂質異常、肥満、喫煙などが動脈硬化を進める原因となります。

歯周病とは
歯周病はプラーク性細菌を原因とする炎症性疾患です。炎症が歯肉に限局される歯肉炎と、歯槽骨破壊によって支持組織の喪失を伴う歯周炎があります。歯周病は日本人中高年において約80%がかかっているとされており、抜歯の主要な原因になっています。歯周病治療では、患者さん本人の的確なブラッシングと歯周ポケット内のプラークや歯石を取り除くことで炎症の改善を図ります。歯周病が改善しても再発リスクを少なくするために定期的なメンテナンスは必須です。
歯周病が糖尿病に及ぼす影響
歯周病治療により慢性炎症が改善されると、インスリン抵抗性が軽減され血糖値が改善されるという報告は数多くあります。2型糖尿病では、歯周病治療により血糖が改善する可能性があるので治療を推奨しています。また逆に糖尿病と歯周病の関係については古くから多くの論文が発表されていて、糖尿病は歯周病に対する危険因子であることが明らかになっています。(歯周病は糖尿病と関係なく発症します。)
歯周病が血糖上昇に寄与する
歯周病が存在すると、歯ブラシとか食事で出血しても一時的に菌血症になります。歯周病という慢性炎症があると、体にとっては持続的な刺激となりインスリン抵抗性を少しずつ確実に強くしてしまい、血糖を上昇させてしまうのです。出血を起こしたところから直接血管に歯周病菌が流れ込むと脳梗塞や心筋梗塞の原因になります。
持続的な高血糖が及ぼす影響
歯周病という慢性炎症によりインスリン抵抗性が亢進することで持続的な血糖上昇が起きて、細小血管の障害や組織の修復の遅延、免疫能力の低下を引き起こしてしまいます。つまり治りが悪くなるということです。当然歯周組織への血流も低下しますから歯周病の治りも悪く、歯周病菌の増加を許してしまいます。高血糖の持続が歯周病の悪化を、悪化した歯周病がさらなる高血糖の持続という連鎖を起こしてしまいます。

歯科治療への影響
糖尿病治療がきちんとされてなかったり、自覚症状がないまま糖尿病になっていると、簡単な抜歯などでも重篤な感染症を引き起こす可能性があります。きちんと治療されていても、急な親知らずの腫れや、歯の根の先の腫れでインスリン抵抗性が亢進して炎症が悪化しやすく重症化することがあります。血糖を急激に下げる効果のある薬を服用されている場合も、急な炎症の対応が難しいことがあります。
歯周病治療の基本はセルフケア
慢性炎症である歯周病の最も大事な治療法はご家庭でのプラークコントロールです。数カ月に一度の定期健診の歯石除去だけでは慢性炎症の歯周病はよくなりません。糖尿病の診断の有無を含めた健康診断が大事なのは言うまでもありません。歯周病治療だけで糖尿病がよくなるわけではありませんが、改善することは明らかとされています。ブラッシング、お互いに頑張りましょう!

宇治市 歯医者 body check なかむら歯科医院