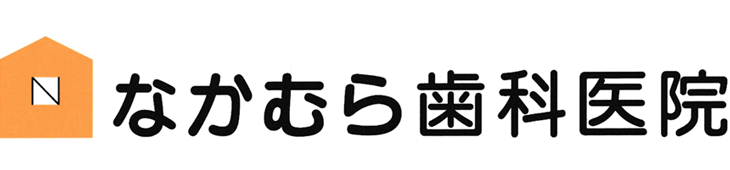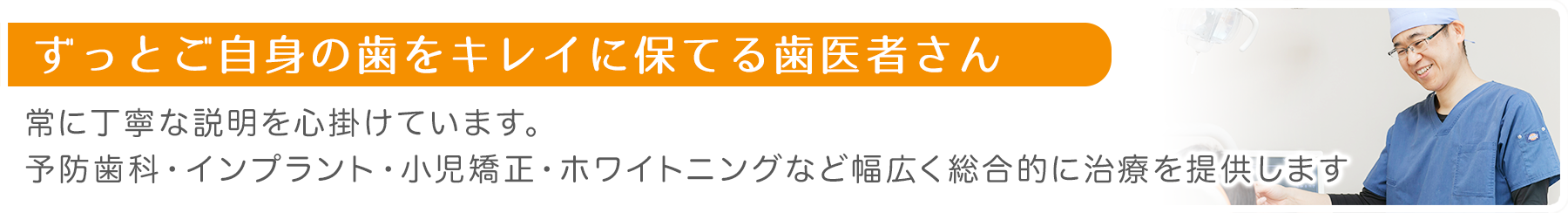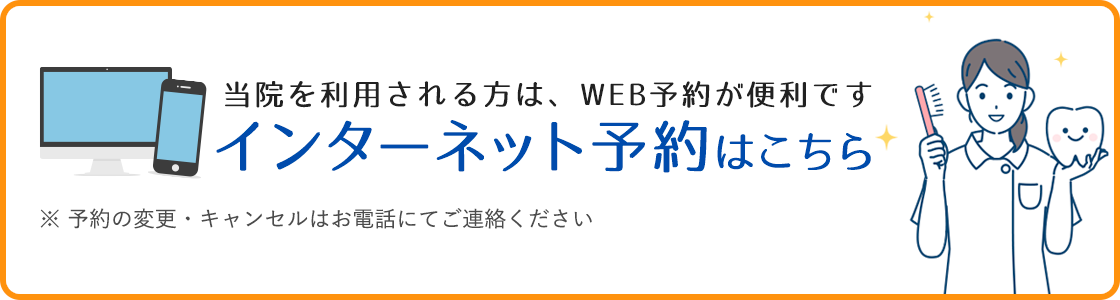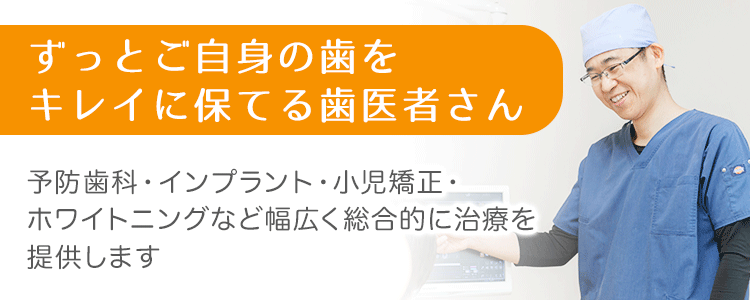目次
口臭対策って何ができる
お口の臭いが気になる、という項目にチェックが付いていたり、お話の中で家族に言われたことがあるとおっしゃる方が少なからずいらっしゃいます。自分で気になるとおっしゃる方はあまりありません。自分で気になる口臭を自覚的口臭、他人から言われる口臭を他覚的口臭と言います。

誰が気になっている?
自覚的口臭
自覚的口臭は、周りの人が感じ取るほどの臭いではない場合が実は多いのです。心理的要因であることが実は多いのです。“自分には口臭があるかもしれない” “話している相手は不快に思っていないかしら” という不安、緊張で唾液が減少していることもあります。口の中が乾燥していると口臭の原因になります。
他覚的口臭
他人が感じ取れる口臭のことです。明確な物理的または生理的な原因があることが多いです。原因として
口腔内の問題には何がある
虫歯でできる歯の凹みに残っている腐敗産物の臭い
歯周病の原因となる歯石やプラークが蓄積されたことによる臭い
舌の上に付着する舌苔の臭い(舌に付く垢と思ってください。)

全身疾患が原因のこともある
糖尿病
一般的に「甘酸っぱい臭い」または「果物が腐ったような臭い」と表現されます。血糖値が高くなると、ケトン体という物質が産生されます。それが呼気や汗、尿にアセトン臭となって現れるのです。栄養不足や低炭水化物ダイエットによっても同じくケトン体が増加します。
肝疾患や腎疾患が進行すると、代謝や老廃物の排出に異常が生じ、特有の口臭が現れることがあります。簡単に言えば、体内の老廃物が代謝・排出されないことが原因です。

肝疾患
甘く腐敗したような臭いがします。特に、肝硬変や重篤な肝不全の場合に発生します。肝臓の機能が低下すると、血中のアンモニアやメチルメルカプタン(硫黄化合物)などの代謝が不完全になります。それらが呼気中に排出され、特有の臭いを引き起こすのです。
腎疾患
尿のような臭い(尿毒症性口臭)が特徴です。腎不全や慢性腎疾患などで見られます。腎臓が老廃物を排出する機能を果たせなくなると、血液中の尿素が増加します。この尿素が分解されてアンモニアを生成し、口臭の原因になります。
胃腸の問題
胃の方から述べていきます。
胃の影響による口臭の特徴は、酸っぱい臭い、腐敗したような臭いです。原因として
逆流性食道炎
胃酸や食べ物が食道へ逆流し、臭いが口まで上がってきます。あの酸っぱく感じるやつです。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染
ピロリ菌が胃の炎症を引き起こし、特有の硫黄臭を伴う口臭を生じます。温泉街のあれです。
胃の消化不良
胃での消化が遅れることで食べ物が胃内で腐敗し、臭いガスが発生します。
腸内環境の乱れ
腸内に原因があると、腐敗臭やガス臭に似た臭いがします。腸内細菌のバランス崩壊(腸内フローラの乱れ)で悪玉菌が増えると、硫化水素やアンモニアなどの臭いガスが腸内で発生し、血液を介して肺から排出されます。また便秘や腸閉塞で腸内に便が長時間滞留すると、腐敗が進み、臭い物質が体内に吸収され口臭の原因になります。
特定の食べ物や嗜好品も原因になる
イメージがつきやすいですよね。そのようなものばかり食べたりしないと思いますが、簡単に記していきます。摂取した物質が消化吸収後に代謝されて体内から臭い成分が排出されます。
臭いの強い食品
ニンニクや玉葱、ネギやキャベツ、大根などは、含有される硫黄化合物が口腔内や消化後に強い臭いを発生させます。代謝された硫黄化合物は血液を介して肺に達し、呼気として排出され臭いを発生させます。
発酵食品や魚類
納豆、キムチなどの発酵食品は特有の強い臭いが口腔内に残りますし、青魚(サバ、イワシ)も腸内でトリメチルアミンという化合物が生成されると、口臭の原因になることがあります。
アルコール
アルコールが分解される過程で生成される物質(アセトアルデヒドなど)が血液を介して肺に排出され、特有の臭いの原因となります。アルコールには脱水効果があって、唾液の分泌を抑え、口内乾燥を引き起こすことも臭いの原因になります。また、過剰摂取すると代謝が乱れ、ケトン体が増えて更なる原因となります。
コーヒーや香辛料
コーヒーは酸性度が高く、唾液の分泌を抑えることで口内を乾燥させ、臭いを増幅させます。香辛料(カレー、クミンなど)は、成分が揮発しやすく、持続的に臭いを残すことがあります。それとはっきりわかる臭いですし、あまり気にならないと思います。
タバコ
タバコの成分(ニコチンやタール)が歯や舌に付着し、持続的な臭いを生みます。いわゆるヤニ、ですね。喫煙により唾液の分泌が抑制され、口内乾燥するので口臭を悪化させます。また歯周病や歯肉炎のリスクを高くします。

全身疾患が疑われるのは?
口臭が強く、食事内容や歯磨きに関係なく続く。特に甘酸っぱい臭いや尿臭を感じる場合、肝疾患や腎疾患が進行している可能性があります。また胃もたれ、胸やけ、便秘、下痢などの場合でも、早めに内科や専門医を受診された方がよいでしょう。
口臭対策として考えられる生活改善は
脂肪分や刺激物を控える胃に優しい食事にする
緑茶やパセリ、ミントなどの消臭効果がある食品を摂取する。またリンゴやセロリは唾液分泌を促します。
適切な水分補給で口腔内を潤し、乾燥を防ぐ
プロバイオティクスや食物繊維を積極的に摂取して腸内環境の改善を図る
適度な運動で腸の働きを促進。
食後に歯磨きや舌磨きを行い、臭いの元となる成分を口腔内から取り除くなど口腔ケアを徹底する
禁煙または減煙(喫煙による口臭は口腔ケアだけで解消が難しいので、禁煙がベスト!です)
アルコール摂取後は水を多めに摂って口腔内の乾燥を防ぐ。
口臭の一時的な対処法として、ガムやマウスウォッシュの活用や消臭サプリメントを用いることもありますがそれはあくまでも一時的なものです。生活改善だけでは口臭は改善しません。原因へのアプローチが必要です。
口臭の原因は先に述べた原因もありますが、原因の90%以上が口腔内にあります。
原因として考えられるのは歯垢の取り残しです。歯面に付いた歯垢が虫歯の原因になり、歯茎に炎症を起こし歯周病の原因となります。虫歯で歯に穴が開くと物が詰まり、それが腐敗して臭いの原因になります。保険の金属の詰め物などは、経時的に酸化します。セメントの劣化とあいまって歯と金属に隙間が出来て虫歯になったりします。セラミクスや金が良い点の一つは、材料が酸化しなくて虫歯になりにくい点です。唾液が減少して口腔が乾燥して細菌が増殖することも口臭の原因ですが、歯垢の除去不足がかなりの割合を占めています。皆さん磨いていらっしゃると思いますが、歯垢をほぼ完璧に取り除けていますか?磨いているのと磨けていることは違います。もちろん≒の方もいらっしゃいます。
口臭予防のために歯科医院に行く、いいですね!
歯垢の除去が全身疾患が原因でなければ一番の予防であり、対策です。各個人によって口腔内は千差万別で、磨きやすい形態の方、磨きにくい方、部分的に磨きにくい方、口が開きづらい方、歯茎が下がっている方、親知らずまで生えている方、親知らずが斜めに生えていてそのままにしている方、などなど。人それぞれ磨き癖もあります。歯垢の残り方もそれぞれです。出来る限り歯垢を取り除くために、その方に合った磨き方を覚えていただきたいと思います。衛生士さんに是非教わってください。それでもウィークポイントはあります。定期的に来院していただきプロの力を借りてウィークポイントのケアをする、それが良いと思います。

口腔内のケアのポイント
歯と歯茎の境目を丁寧に優しく磨く。
フロスや歯間ブラシを使用する。
舌苔の除去(舌ブラシや舌クリーナーを使用。週1~2回)
洗口液はあくまでも補助的であることを認識して使用する。
毎日できれば食後と寝る前のブラッシング習慣を身に付けましょう。